「お金」には「価値」がありますが、それはどのようなカラクリで生まれるものなのでしょうか。
<参考過去投稿>
金融資産と実物資産の種類|保有資産の分類と把握
今回は、『モズラーの名刺』という小話から、考えてみます。
ババ抜き貨幣論
どうやって、お金は価値をもつでのでしょうか。
まずは、私たちがお金を「価値あるもの」として受け取る理由を考えてみましょう。
たとえば、日給1万円のバイトをして、1万円分の南アフリカの通貨「ランド」でもらったら、どうでしょうか。
南アフリカに行く予定がある人以外にとっては、ほぼ価値を感じない(少なくとも1万円分の価値は感じない)かと思います。
これは、南アフリカ・ランドをもらっても、日々の生活に「使えない」からではないでしょうか。
つまり反対に考えて、日本円というお金に価値を感じるのは、日常の生活に使えるから、言い換えると、他の人が「受け取ってくれる」からと言えるかと思います。
個人の観点から考えれば、お金に価値を感じるのは、また他の人が受け取ってくれて通貨として使えるから、という風になりそうです。
しかしこれでは、誰かが受け取ってくれる限りは大丈夫、誰も受け取らなくなったら負け、というまるで「ババ抜き」のような貨幣観になってしまいます。
誰かが受け取ってくれる限りは価値をもつ、これをみんなが信じている、という共同幻想は間違ってはいないかもしれませんが、お金が価値をもつカラクリとしては釈然としません。
モズラーの名刺
お金の価値について、別の見方ができる、『モズラーの名刺』という小話を見てみましょう。
**********
モズラーには2人の子供がいました。
モズラーはその兄弟が家のお手伝いをしてくれるたびに、自身の名刺を1枚渡しました。
兄弟にとっては、名刺がどういうものかよくわからず、ただ父親の名前が書いてある自己紹介カードみたいなものでした。
ある日、モズラーは兄弟に言いました。
「みんながお手伝いをしてくれて助かっている。これからもみんなで家事を手分けしてやっていくために、毎月月末の夜に10枚の名刺をそれぞれ渡してほしい。
10枚の名刺を渡せなかったら、その翌月はゲームを没収することにする。今までと同じく、お手伝いしてくれるたびに名刺を1枚渡すから、頑張ってお手伝いしてほしい。」
兄弟は、これを聞いてより一層もお手伝いを頑張りました。
月末が近づいてきたとき、兄はお手伝いで20枚の名刺をもっていた一方、弟は遊びに夢中で9枚しか名刺を手に入れていませんでした。まだ月末の夜までお手伝いをする時間はあります。
弟は兄に提案しました。
「このお菓子を1つあげるから、兄ちゃんの名刺を1枚くれないか」と。
兄もそのお菓子がほしかったので、名刺1枚を渡して弟からお菓子をもらいました。
これをきっかけに、兄と弟の間では、お菓子やおもちゃを名刺と交換するやりとりが生まれました。
**********
モズラーの名刺からの考察
上の小話から、以下2つの考察が得られます。
1.名刺に「引き換え」を導入することで価値が生まれる
(税金徴収の導入で貨幣に価値が生まれる)
月末に10枚の名刺を、父親であるモズラーへ渡さないと、翌月にゲームができなくなる、というルールを導入しました。これにより、兄弟にとって名刺は「翌月もゲームをするためにお手伝いして得るもの」と認識するようになります。
兄弟にとって名刺は、ただの紙切れから、「価値」をもつものに変わったのです。
これは、国家/国民/貨幣の構図に当てはまります。
日本国が「円」で税金を徴収すると定めて納税の義務を国民に課し、納税しないものには罰則が与えられるとします。
日本国は公共事業等の対価として日本円を国民に配ります。国民は税制に従い納税します。
このように「税制」を導入することで、紙切れの「日本円」に価値が生まれます。
2.名刺に価値があればモノとの交換にも使われる
(価値ある貨幣は交換手段として流通する)
紙切れだった名刺に価値が生まれたので、兄弟の中でモノの交換に使われるようになりました。
交換手段・計算尺度・価値保存の3機能(以下参考)をもたせられる名刺は、「お金」として機能するようになったということです。
<参考過去投稿>
お金の仕組みってどうやって生まれたの?①お金がもつ3機能
これもまた、国家/国民/貨幣の構図に当てはめてみましょう。
価値をもつ日本円を得るための手段は公共事業だけでなくなり、やがて国民間で直接やりとりされるようになります。
これが民間企業にあたります。
食べ物をもらう、モノや人を運んでもらう、家を建ててもらうなどなど、何かを人にお願いするために「日本円」を渡します。
その「日本円」を得るために食べ物を売ったり、モノや人を運んだり、家を建てたり、誰かの役にたつ仕事をします。
こうして、民間で人と人が助け合う社会が形成され、日本円はその媒介をする存在となります。
まとめ
上記のモズラーの名刺やそれを国家/国民/貨幣に当てはめた例はあくまで思考実験なので、お金や社会の歴史を語るものではありません。
しかし、お金と社会の関係について理解するための一つのカラクリとなります。
「租税こそが貨幣に価値を生み貨幣を動かす」
「動く貨幣は、みんなが助け合う社会の媒介として機能する」
政治や経済、金融など小難しい事情を排除しても、上記のような簡単な仕組みで「お金」ができてしまうのは、非常に面白い切り口だと私は感じます。
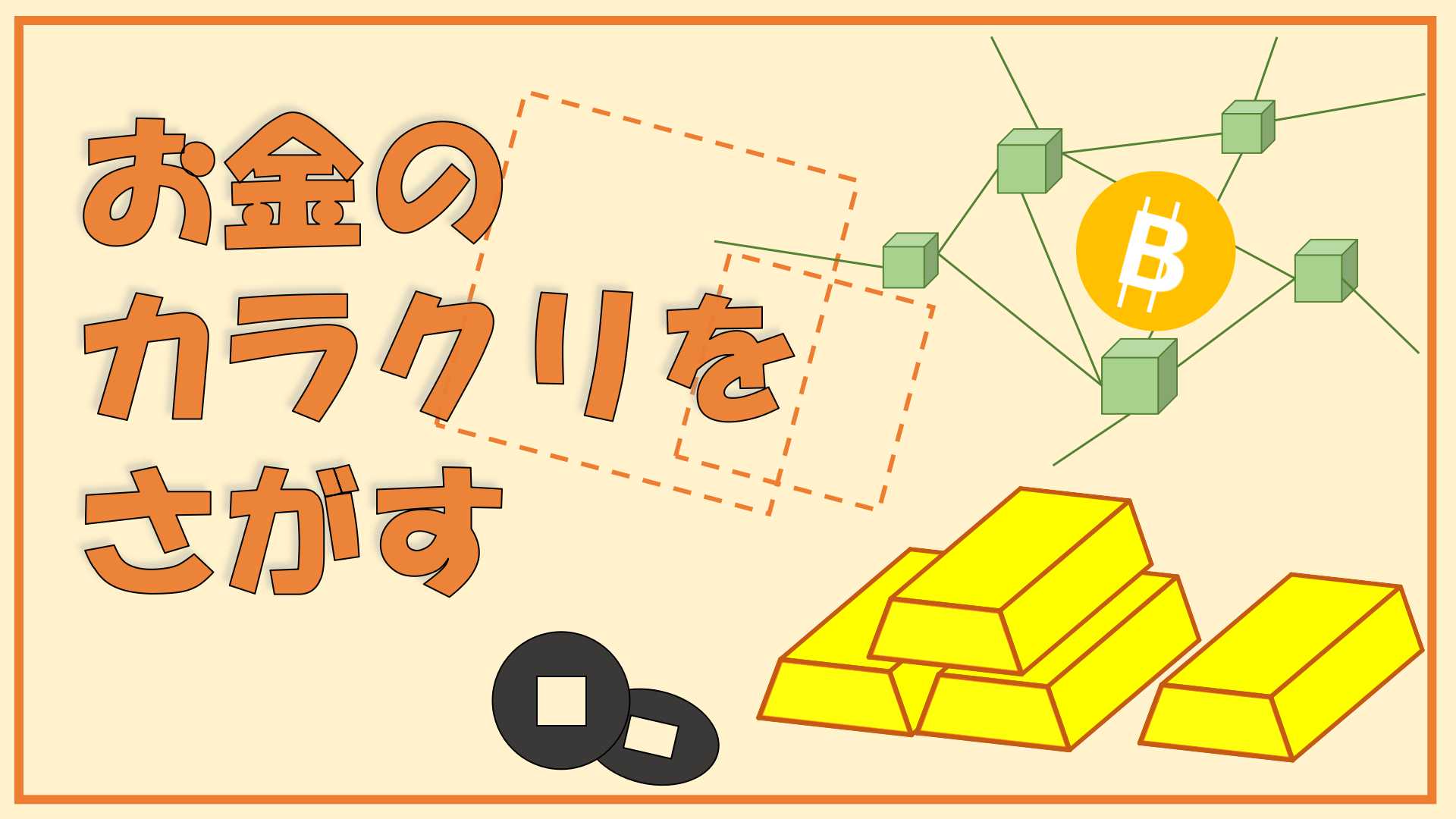
コメント